
稲荷信仰
農耕民族である日本人は古来より「米」を命の根源として崇め祀ってきた。
先人達は自然を畏敬し、豊作を願った。
「米」は豊かさの象徴であり貨幣と同じように扱われた。
稲荷神のご利益が主に商売繁昌・事業発展・家内安泰・子孫繁栄とされるのはそれゆえである。
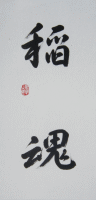
村上三島氏 書
五穀豊穣を感謝し、万民豊楽の神霊として語り継がれてきた稲荷信仰はまさしく稲魂(自然神)そのものである。

最古の宝船(多加良富年)
日本人にとって米は宝であり、最古の宝船には稲穂をのせただけのシンプルなものであった。後に米俵になり、七福神がのるようになったのは江戸時代になってからのことである。

仕事・実り守
豊臣・徳川時代の稲荷信仰

大坂城の南東にあり、大坂城三ノ丸に位置した当神社。
西向きに建てられている本殿は比較的に少なく大坂の経済を見守るため、西を向いていたとも言われている。
大坂の町を造った豊臣秀吉公は稲荷神を崇敬し当神社を大坂城の鎮守神として祀った。また、大坂城における神事の多くは当神社神職が執り行い、慶長八年には豊臣家より五百石の水田(現・大阪市天王寺区玉造本町)が当神社へ朱印地として寄進された。
摂津名所図会(当神社の図)

伏見と玉造のおいなりさんの��出会いを描いた絵図
「摂陽奇観」より
古くから五幸稲荷大明神として崇敬者に慕われ、江戸時代には創祀年代の古さから地元では「もといなり」と言われていた。
伏見稲荷大社のご分霊を直接祀らない稲荷社で、豊臣秀吉公が稲荷の信仰者であったことや伏見の住民を玉造の地へ住まわせた関係で稲荷神を特に崇められたと考えられている。

稲荷社十五社巡り:
玉造御本社と記され、大坂・稲荷社の本社として崇められていた。

当神社新嘗祭(11月23日)
当神社水田で作られた古代米を奉納

当神社境内にある水田
現在も古代米が地域住民・崇敬者により作られている

まけず・おとらず三ヶ津自慢競:
江戸時代の江戸・京都・大坂の自慢くらべ。稲荷神社の部には、江戸・王子のいなり、京都・伏見のいなり、大坂・玉造のいなりと記されている。
